※本紹介内容はANECのHP(https://anec-in.com/)より引用しております。
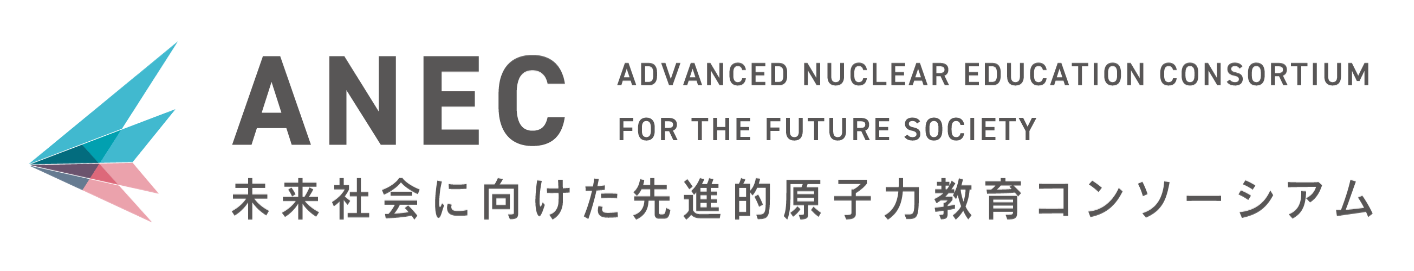
概要
スケールメリットを人材育成に生かし切る、日本初の試み、ANEC始動。
暮らしや社会、経済活動は、多くのエネルギーを消費することで成り立っています。そこから排出される温室効果ガスは地球温暖化を招き、気候変動を引き起こす要因になっていると指摘されています。日本が脱炭素社会に向けて大きく舵を切った今、エネルギーの在り方を深く考えていかなければなりません。2021年10月に決定された「第6次エネルギー基本計画」には、「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが、エネルギー政策の原点」とあります。原子力発電の安全性をすべてに優先させたうえで、社会的な信頼を得、安定的な利用を進めていくには、優れた原子力人材が必要です。
しかし、足元を見れば、近年の原子力に関わる学部・学科の改組などにより、高等教育機関における原子力の人材育成機能は低下の傾向にあり、継続的かつ安定した人材輩出は難しい局面を迎えています。
すなわち、今後わが国では、原子力人材に対する需要と供給のギャップが、拡大していくことが予想されます。今こそ、原子力分野の人材が、社会から必要とされています。
原子力分野を力強く支え、原子力イノベーションを先導する人材の育成を目的に、『未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム(Advanced Nuclear Education Consortium for the Future Society:ANEC)』が立ち上がりました。学生個々への教育・研究を、(学生が所属する)一つの教育機関で完結させるのではなく、多様な教育資源を有する組織の紐帯の中で展開していくのは日本初の試み。原子力がつくる持続可能な未来社会がここから始まります。
目的
各組織・機関が補い合い高め合いながら、未来社会が求める原子力人材を育みます。
- 多様な専門性を有する原子力人材の要請に継続的に応えていくため、大学や研究機関、企業が高度に連携・協働し、各組織や機関が有する教育リソース(教員、カリキュラム、実験・実習プログラム、原子炉などの実験施設・装置など)を相互補完することで、一体的な人材育成を推進します。
- 国際機関や海外大学との密接な連携を通じて、各国の先端研究の息吹に触れ、広い視野と多様な価値観の修養を促す機会を提供します。
- 興味と関心に応える開かれた教育により、“総合工学”としての原子力の魅力と可能性を広く伝えていきます。
組織図

教育内容
座学、実験・実習、国際経験、産業界・他分野との連携、原子力人材に必要とされる最高水準の教育を準備しています。
1構成機関の相互補完によって高度化された体系的な専門教育カリキュラム
- 原子力に関する主要な基礎・基盤科目
- 各大学で開講されている講義の内容を共有
- 講義資料のオンライン化・オープン化による時間と場所を選ばない学習
- 社会人向けリカレント教育
2原子力施設や大型実験施設等を使った実験・実習
- 原子力施設や大型実験施設の効果的・効率的な共同利用・実験実習
- 電源立地地域での学生の就業体験(インターンシップ)
3国際機関や海外の大学との組織的連携による国際研鑽機会
- 短期留学、国際リーダー育成に資する合宿形式のワークショップ
- 同じ志を持つ学生等の交流によるグローバルな人的ネットワークの構築
4産業界や他分野との連携・融合
- 産業界からの外部講師による実践的な講義
- 人文・社会科学分野をはじめとする多様な分野と原子力のかかわりに関する科目

事務局長あいさつ
事務局長 中島 宏
北海道大学 大学院工学研究院 原子力安全先端研究・教育センター 副センタ―長 特任教授
 未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)は、次世代の原子力人材育成を目指し、産学官が連携して教育・研究の発展に取り組むプラットフォームです。学校教育のみならず、リカレント教育、生涯教育まで幅広い視点でカリキュラムや教材を開発し、社会との共生や国際的視野を持つ人材の育成を推進しています。多様な分野の専門家と協力し、未来を支える人材育成に努めてまいりますので、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)は、次世代の原子力人材育成を目指し、産学官が連携して教育・研究の発展に取り組むプラットフォームです。学校教育のみならず、リカレント教育、生涯教育まで幅広い視点でカリキュラムや教材を開発し、社会との共生や国際的視野を持つ人材の育成を推進しています。多様な分野の専門家と協力し、未来を支える人材育成に努めてまいりますので、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
グループ会議紹介
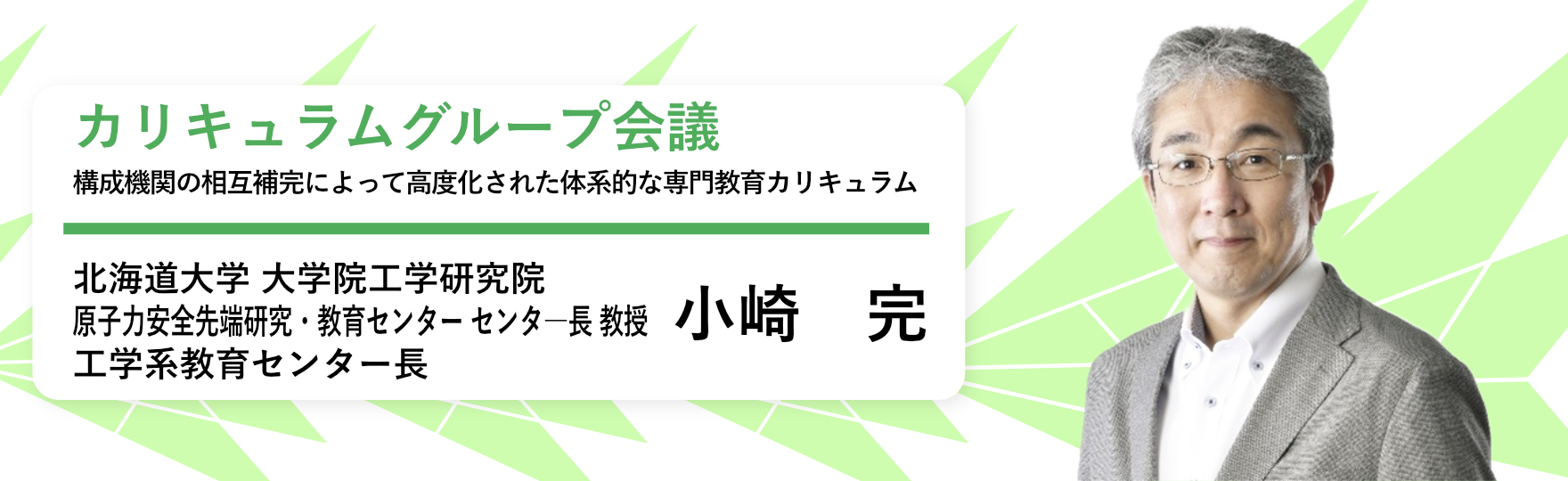
全国の大学、高等専門学校、研究機関、民間企業等が連携して、大学等や一般の方々のためのカリキュラムを構築しています。また、そのカリキュラムに沿って、何時でも誰でもどこでも活用できるオンライン教材の制作・公開を進めている他、制作したオンライン教材をもとにした大規模公開オンライン講座(MOOC)を制作・開講することで、幅広い年齢層へ学習機会を提供しています。一方、オンライン教材と組み合わせることで教育効果を高めることのできる、実験・実習、国際インターンシップ等の教育プログラムを検討・実施しています。オンライン教材の体系的、網羅的、階層的な拡充とともに、学習証明(デジタルバッジ)の導入による学習意欲の向上ならびに学修歴への意識向上が大きな課題です。
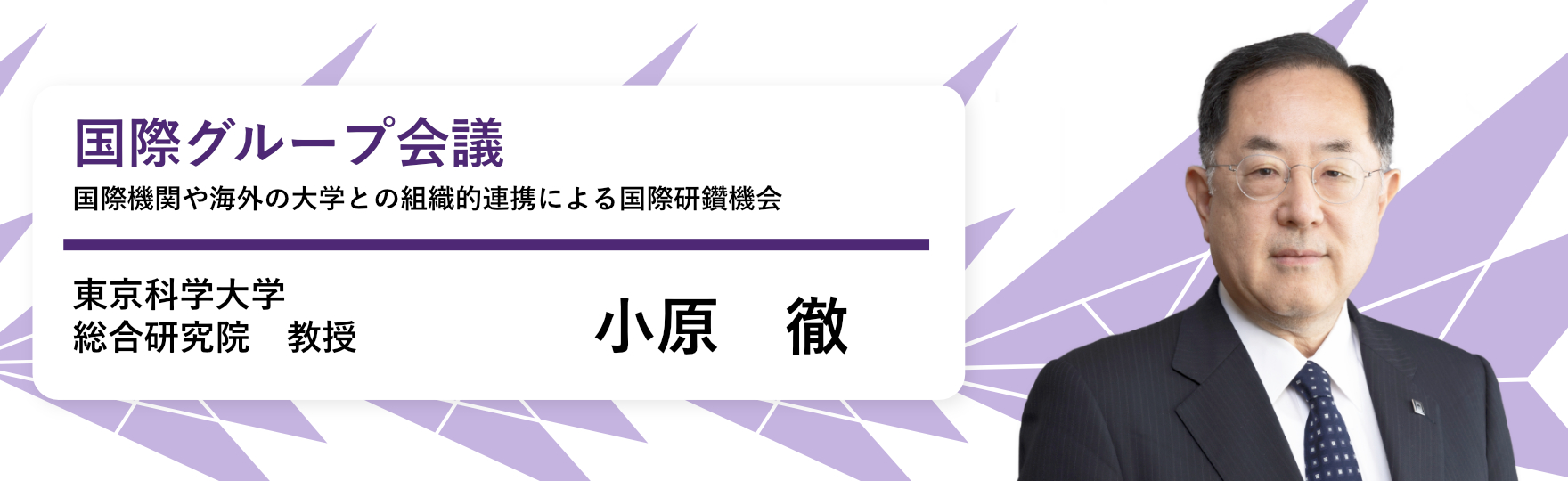
人材育成のテーマとして、原子力工学の基礎に立脚し、エネルギーシステムと様々な工学分野の先端技術に通じ、原子力分野で新たな企業活動を立ち上げる意欲と能力を持ち、国際的センスとマネジメントに優れた将来の原子力エネルギー分野でのイノベーションを担うことのできる技術者・研究者の育成を本人材育成活動を取り上げている東京科学大学を中心に、海外での実習等の活動を行っている課題と連携し、国際機関や海外の大学との連携による国際研鑽の機会を学生等に効果的に提供してまいります。
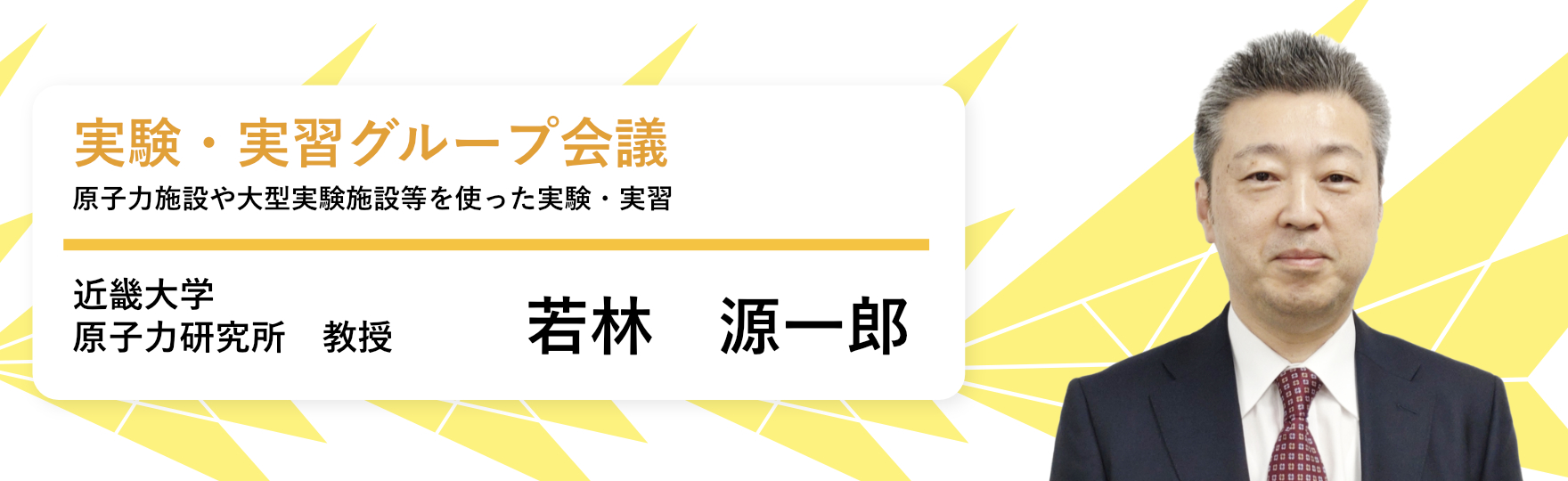
国内に残された貴重な原子力教育リソースである近畿大学原子炉UTR-KINKIと京都大学臨界集合体実験装置KUCAや東北大学の持つ大型実験施設等を利用した実習を、体系的に再構築・強化して利用者に提供します。また、原子炉や大型実験施設等を有する大学が持つ原子力教育リソースを相互に提供し合って教育機能を補い合い、原子力専門教育の強化と原子力産業界及び原子力アカデミアへの人材供給を目的とした教育拠点を形成します。
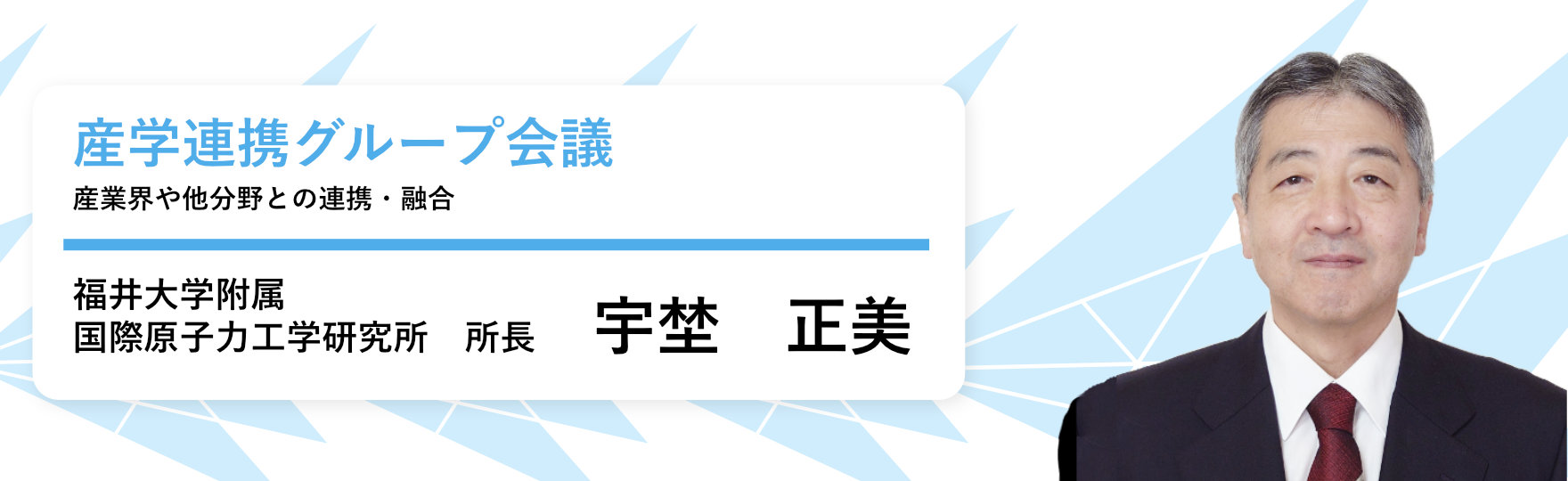
原子力施設を持つ日本原子力研究開発機構、関西電力、日本原子力発電株式会社の福井県嶺南地域の原子力事業者および国際的な人材育成事業を展開している若狭湾エネルギー研究センター福井県国際原子力人材育成センターとの産学連携の下で、関西・関東圏の大学とも連携して、嶺南地域をモデルとした新たなリカレントカリキュラムの検討等を行います。
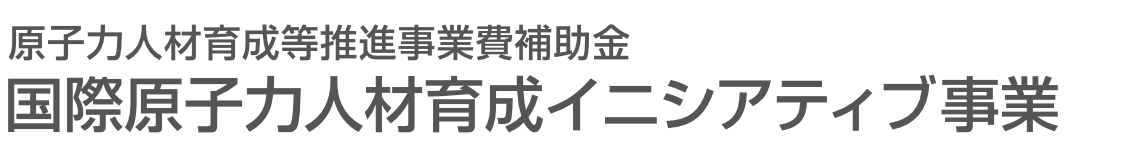
 ANECのカリキュラムページこちら(外部リンク)
ANECのカリキュラムページこちら(外部リンク)