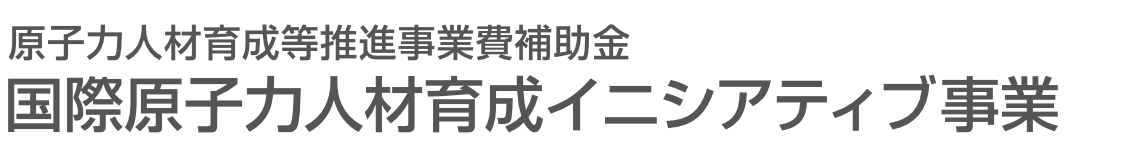東京大学
東京大学
リサイクルの視点をもつ戦略的な廃止措置マネージメント人材育成
事業の背景
原子力を学び、将来生業とする者は、原子力工学を学ぶは当然のことです。しかし、これに加え自分たちの仕事が、世間の中でどのように見られているかを社会科学に基づき多角的に把握することが原子力の将来にわたる利用継続の喫緊の課題とも言えます。
特に、バックエンド(廃止措置や低レベル放射性廃棄物(LLW)等)の推進には、社会科学による客観的な分析と判断、また、それに基づく交渉力が不可欠です。
客観的な分析と判断は、「ISO21500プロジェクトマネジメント」の提唱している手順に従い進めていき、「原子力のリスク」だけではなく、バックエンド事業の取り巻く「ビジネスリスク(好機のリスク、脅威のリスク)」を抽出します。バックエンド事業が相対している事業者の内部及び外部の環境を把握できるようなスキルを身につけるものです。一方、廃止措置中の原子力発電所は、基本的に廃棄物の塊であり、適切な分類を行い、リサイクルや処分を進めていくことが必須です。廃止措置にも「リサイクル」の概念を積極的に取り入れていくことが望まれます。
ただし、プロジェクトマネジメントは、原子力技術者にとってスキルの一つであり、原子力、特に、廃止措置やLLW等の工学の知識、知見及び経験の上に蓄積して来るものです。本事業では、この両方について人材育成プロブラムを構築し、研修を行っていきます。
事業の目的
バックエンド分野における廃止措置、低レベル放射性廃棄物などに対して事業許可、認可の申請書を題材として、申請書が作成された時点と現在との新規技術の差や知見、国際的な動向、及び、社会科学の観点に立った新たな世論や批判についてISO21500マネージメント手法を適用し、分析と判断を行うことを目的とし、プロジェクトマネジメントの根幹である「戦略」に反映していくことをメインプログラムとします。このプログラムは、集合研修とし、実習(国内で実施する現地実習と、海外で実施する海外研修)を行います。
実習の効果を最大限引き出すために、実習の前後を含めて総合的なプログラムを実施します。

Menphis Processing Facility にて現場視察

Erwin Resin Processing Facility にて議論